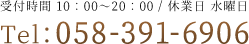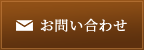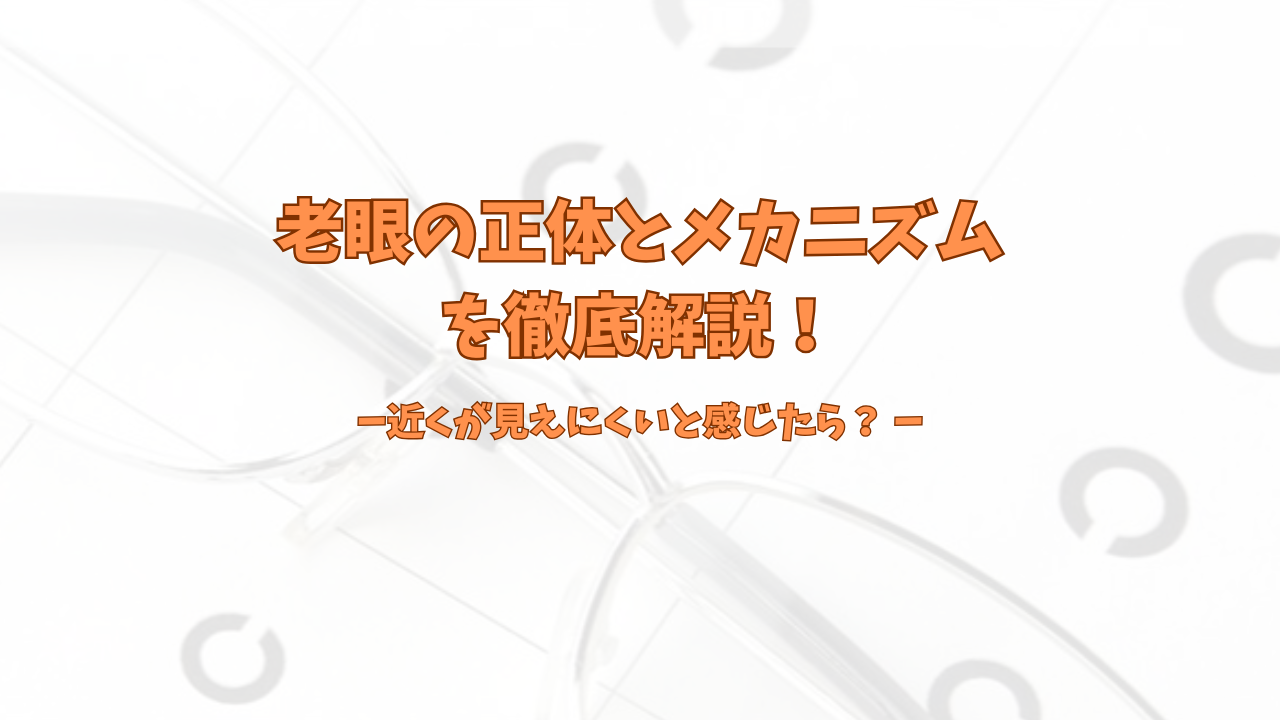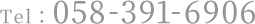「最近、本を読むときに文字がぼやける…」「スマホを見るとき、つい遠ざけてしまう…」
そんな経験はありませんか?もしそうなら、それは老眼(ろうがん)かもしれません。
今回は、多くの人が経験する「老眼」が一体どんな状態を指し、
なぜ起こるのか、そのメカニズムについて詳しくご紹介します。

老眼とはどんな状態?具体的な症状
老眼とは、加齢に伴い、一番遠くから一番近くまで見える視界の幅が少しずつ狭まっていく状態を指します。
具体的な症状は、日常生活で以下のように現れます。
• 近くの文字が見えづらくなる:特に新聞や本、スマートフォンの小さな文字が読みづらくなります。
• 物を見る際に距離を離すようになる:見えにくい文字や物を、顔から離さないとピントが合わなくなります。
• メガネの着脱を頻繁に繰り返す:遠くを見る時はメガネをかけ、近くを見る時(新聞を読む時など)は外したり、
またかけたり、近づけたり離したりを繰り返すようになります。
• 遠くと近くの切り替えが困難になる:パソコン作業中にテレビを見たり、
車の運転中にカーナビと遠方の景色を交互に見たりするなど、
様々な距離を頻繁に見るライフスタイルで不便を感じることが多くなります。
特に、若い頃に近視で、メガネを外すと近くがよく見えていた方も、老眼が始まると近くもぼやけて見えるようになることがあります。

老眼のメカニズム:なぜ近くが見えにくくなるのか?
私たちの目は、カメラのレンズのように水晶体(すいしょうたい)と呼ばれる部分が厚みを調節することで、
遠くも近くもピントを合わせています。目に入ってきた光は、まず角膜で約7割が屈折し、残りの屈折を水晶体が微調整して、
網膜の上に焦点を結ぶようにしています。遠くから来る光と近くから来る光は目に入ってくる角度が異なるため、
水晶体はこの厚みを調節して、どちらの光も網膜に焦点を合わせるように働いています。
しかし、老眼は加齢とともに、この水晶体の機能が変化することで起こります。
1. 水晶体の弾力性低下
若い頃は弾力性があり、自由に厚みを変えることができた水晶体が、
年齢を重ねるごとに弾力性を失い、硬く、丸くなりにくくなります。
2. 焦点の位置のずれ
遠くの物に焦点が合っている状態(裸眼で遠くが見える人、またはメガネで遠くが見える近視の人)で、
近くの物を見ようとすると、近くから来る広がりながら入ってくる光を水晶体が十分に屈折させることができません。
その結果、本来網膜上に結ぶべき焦点が、網膜よりも後ろに結ばれてしまいます。
3. 見え方の変化
この状態では近くの物がぼやけて見えます。物を遠ざけることで、
光の広がりを小さくし、無理やり網膜上に焦点を合わせている状態になります。
4. 老眼の進行
時間の経過とともに水晶体の弾力性はさらに低下し、より遠ざけないと見えなくなったり、
最終的には遠ざけてもはっきりと見えなくなる状態へと進行します。
つまり、老眼は、水晶体がピント合わせのために厚みを変える能力が低下することによって、
近くの物に焦点を合わせることが難しくなる状態なのです。
老眼と早期の対策の重要性
「まだ若いから」「老眼を認めたくない」という理由で、老眼のサインを感じても対策を我慢してしまう人がいます。
しかし、これは逆効果になることが多いです。
• 慣れやすさの違い
老眼の度数が強くなればなるほど、メガネを使った際の歪み(見えにくいゾーン)が大きくなり、
足元がふわふわして見えたりするなどの違和感が強くなるため、慣れるまでに時間がかかります。
• 早期使用のメリット
度数が弱い早い時期から遠近両用メガネを使い始めることで、歪みが少なく、足元もぼんやりと見えるため、
スムーズに慣れることができます。外見上も境目がなく、見た目の抵抗も少ないため、早めの使用がおすすめです。
また、もともとメガネをかけたことがない人、特に遠視気味で若い頃から視力が良かった人ほど、
老眼のメガネをかけ始める際に慣れるのに時間がかかる傾向があります。
これは、プラスレンズ(凸レンズ)によって物が大きく見えたり、揺れを感じやすいため、より違和感が強く出るためです。

まとめ
老眼は誰にでも起こりうる自然な加齢現象です。近くが見えにくいと感じ始めたら、
それは老眼のサインかもしれません。放置せずに早めに適切な対策をとることで、
視界のストレスを減らし、より快適な日常生活を送ることができます。
ご自身の目の状態やライフスタイルに合ったメガネを見つけるためには、
ぜひ専門家である眼鏡店や眼科で相談してみてください。