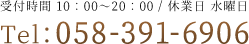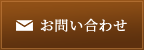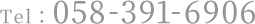こんにちは。
岐阜県羽島市の認定補聴器技能者の山村です。
今日は補聴器を使いこなすコツについて
書いていきます。

補聴器を使いこなすための4つのコツ
1.起きている間は常に装用する:
補聴器に慣れるためには、静かな場所でも一人でいる時でも、
寝る時以外は常に補聴器を装着し続けることが重要です。
これは、脳が補聴器から入る新しい音の感覚に慣れるための
「可塑性(かそせい)」を最大限に活かすためです。
たまにしか使わないと、せっかく慣れた音の感覚を忘れてしまい、
慣れるまでに余計に時間がかかってしまいます。

2.最初から理想の聞こえを求めない:
補聴器をつけた瞬間に「はっきり、くっきり」聞こえるようになるという
過度な期待は、がっかりの原因になります。
最初は、一日中つけていられる程度の音量から始め、少しずつ音量や調整を
上げていくのが理想的です。特に、加齢性難聴で聞き取りにくかった高い音は、
補聴器で増幅されると最初は「キンキン響く」ように感じることがあります。

3.補聴器は万能ではないと理解する:
補聴器は音を増幅する機械であり、人間の複雑な耳の機能を完全に補うことはできません。
「聞きたい音だけを大きくする」「騒音の中から特定の声を選ぶ」といった高度な聞き分けは、
補聴器ではなく脳の働きによるものです。補聴器はあくまで音を脳に届ける手助けをするツールであり、
その音を分析し言葉として理解するのは脳の役割です。

4.使いこなすには時間がかかることを理解する:
補聴器に慣れるまでには、個人差がありますが、
一般的に3ヶ月から6ヶ月、長い場合は1年ほどかかると言われています。
焦らず、地道に装用を続けることが成功の鍵です。途中で諦めず、定期的に専門家による調整を受けながら、
根気強く取り組むことが大切です。
家族の協力の重要性:
補聴器を上手に使いこなすためには、本人の強い意志だけでなく、
周囲の家族の協力が不可欠です。
精神的なサポート:
補聴器の装着や電池交換などは、慣れないうちは手間がかかり、
途中で諦めてしまう人もいます。
家族が励まし、応援してくれることで、本人のモチベーションを維持できます。
理解と正しい接し方:
補聴器の性能を過大評価せず、補聴器が苦手な音(高い音、騒音など)があることを理解しましょう
。また、「補聴器をつけても聞こえない」と責めたり、「年寄り臭い」などと
ネガティブな発言をしたりすることは、本人が補聴器の装用を止めてしまう原因となります。
コミュニケーションの工夫:
難聴者に配慮した話し方(後述の「難聴者が聞き取りやすい話し方」を参照)を心がけることも、
補聴器の効果を最大限に引き出す上で重要です。
補聴器は正しく理解し、正しく使い、周囲のサポートがあれば、必ず聞こえの改善に貢献します。

まとめ
補聴器を使いこなすには、
「毎日着けること」「焦らず慣れること」「補聴器の限界を理解すること」
そして「時間をかけて取り組むこと」が大切です。また、ご本人の努力に加えて、
家族の理解と支えが何よりも大きな力になります。補聴器は“すぐに完璧に聞こえる魔法の道具”ではありませんが、
正しく使い続けることで、確実に生活の質を向上させてくれる心強いパートナーです。
焦らず、あきらめず、周囲と一緒に前向きに取り組んでいきましょう。