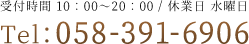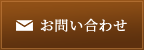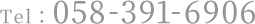こんにちは。
岐阜県羽島市の認定補聴器技能者の山村です。
今回は補聴器のグレード選択における要点を解説いたします。
補聴器には性能によるグレードが存在し、その選択は価格だけでなく、聞こえの質にも直結します。
「買い替えサイクルから考える補聴器のグレード選択」について、その指針と理由、そして注意点を詳しく解説します。
最適な補聴器選びは、個人の耳の状況や生活環境、価値観によって変わってきます。

結論からお話をすると、ご自身が買える範囲内のもので、良いものを買っていただく。
この推奨には、主に二つの重要な理由があります。
理由 1:聞こえにくさは人生に大きく影響する
聞こえにくさ(難聴)は、個人の人生に非常に大きく影響を与えます。
そのため、なるべく良い補聴器を使用し、生活の改善に繋げ、
人生を良くすることが大切だと考えられています。
改善できればできるほど、生活の質の向上に直結します。
理由 2:グレードアップによる性能的なデメリットはない
性能面から見ると、グレードを上げることにデメリットはほとんどありません。
グレードが高いことによる唯一のデメリットは、金額が高くなることだけです。
したがって、金銭的に許容できる範囲内で、より良い性能のものを選ぶことが推奨されます。

なぜグレードが高いと「良い」のか?
グレードが高い補聴器は、聞こえの改善に、より貢献しやすくなる傾向があります。
1. 周りの音や物音の「抑制」に優れている
補聴器で聞こえを改善しようとすると、聞きたい音だけでなく、
周りの音や一部の物音もきつく感じてしまい、結果として音量を上げづらくなるケースが発生しがちです。
グレードの高い補聴器には、そういった周りの音や物音を抑制する機能が搭載されています。
抑制機能が入っているものほど、不快な音を抑えつつ音の改善を進められるため、聞こえの改善に貢献しやすくなります。
2. 性能における「トレードオフ」の解消
補聴器の性能には「トレードオフ」(あちらを立てればこちらが立たず、どちらか一つしか得られない状況)が存在します。
1. 補聴器は、聞き取りにくい人の声(特定の周波数帯)を大きくしようとします。
2. しかし、補聴器は音の塊としてではなく、周波数帯として音を捉えるため、
人の声だけでなく、その周波数帯に対応する物音も大きくなってしまいます。
結果として、利用者は「物音が大きくても声の改善を重視するか」、あるいは
「快適性を重視して声の聞こえを少し抑えるか」のどちらかを選ばざるを得ませんでした。
グレードが上がるほど、このトレードオフを解消しやすくなります。
物音が気にならずに音を上げやすくなるため、聞こえの改善に繋げることができます。

グレード選択時に考慮すべき3つの注意点
グレードの高い補聴器には大きなメリットがありますが、購入前に認識しておくべき注意点が3つあります。
1. 金額差が非常に大きい
グレードの違いは、1万2万といった差ではなく、10万円単位の大きな金額差として現れます。
そのため、機能が良いとわかっていても、それが「購入できるか、できないか」という別の金銭的な問題が生じます。
2. 感音性難聴による性能の限界
補聴器を使用する方の多くは、内耳(音を感じ取る神経の部分)の損傷による感音性難聴です。
この内耳の損傷度合いによって、補聴器の機能が効果的に活きるかどうかが変わってきます。
内耳の損傷度が大きい方の場合、いくら高性能な機能があっても、その効果を感じにくい傾向があります。
これは、単にお金を出せば解決する問題ではありません。機能が活きるかどうかは、その人の耳の状況に依存するのです。
3. 買い替えを視野に入れること
補聴器は、20年や30年といった未来永劫使えるものではなく、買い替えて使用していくことになります。
補聴器の耐用年数は大体5年と言われていますが、現在の円安などの影響もあり、
実際には6〜7年程度のペースで買い替えている方が多いようです。
そのため、購入の際には、その後の買い替えも視野に入れた上で、
聞こえの改善を継続できる状態を維持できるような計画を立てることが非常に大切です。
最終的に、ご自身の聞こえの状況、生活環境、そして金銭的な計画を総合的に考慮し、
「買える範囲内で良いもの」を選んでいただくことが、長期的に見て人生を豊かにするための鍵となります。