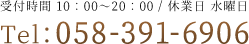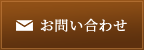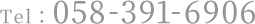こんにちは。
岐阜県羽島市の認定補聴器技能者の山村です。
かつては聴覚障害がある人の運転免許取得は困難でしたが、
日本では2008年6月1日から聴覚障害者も普通自動車免許の取得が可能になりました。
これは、聴覚障害のある人々の社会参加を促進する上で大きな進歩です。
運転免許取得の基準と適性検査 聴覚障害のある人が運転免許を取得する際には、
「適性検査」をクリアする必要があります。
聞こえの基準
10メートルの距離から90デシベルの音が聞こえるかどうかが目安とされます。
これは、自動車のクラクションや救急車、消防車、パトカーなどの
サイレンが聞こえるかを判断するための基準です。

補聴器・人工内耳の利用
補聴器や人工内耳を装用した状態での検査も認められています。
眼鏡をかけた状態での視力検査と同じ感覚です。
検査に落ちた場合:
もしこの適性検査をクリアできなかった場合でも、直ちに免許が取得できないわけではありません。
以下の条件を満たすことで、免許の交付を受けることが可能です。
1.ワイドミラーへの変更
車内のバックミラーを、より広い視野角を持つワイドミラーに変更する必要があります。
2.聴覚障害者マークの貼付
初心者マークと同様に、車の前後(見える位置)に聴覚障害者マークを貼り付ける必要があります。
これらの措置は、聴覚による情報が限られる分、視覚情報を補完し、
周囲に聴覚障害があることを知らせることで安全運転を確保するためのものです。
運転可能車種の拡大と職域の拡大 制度の改正は段階的に進んでいます。
2008年6月1日: 聴覚障害のある人も「普通乗用自動車」(一般的な家庭用サイズの車)
の運転免許が取得可能になりました。
2012年4月1日: 「すべての普通乗用車」に加え、小型トラックなども運転可能になりました。
ただし、この場合もワイドミラーへの変更と聴覚障害者マークの貼付が必須です。
第二種運転免許の取得も可能に
さらに重要なのは、バスやタクシーの運転に必要な「第二種運転免許」も取得可能になったことです。
これにより、聴覚障害のある人が選べる職業の幅が大きく広がりました。
運転時の注意点 聴覚障害のある人は、聴覚からの情報が限られるため、運転時には特に注意が必要です。

方向感覚の困難:
片耳難聴の場合、音がどちらの方向から来ているかを判断するのが難しいことがあります。
これにより、救急車やパトカーの接近方向が分からず、対応が遅れるリスクがあります。
同乗者との会話:
片耳難聴で助手席側の耳が聞こえにくい場合、同乗者との会話が困難になることがあります。
常に周囲に注意を払う:
聴覚情報が少ない分、ミラーを頻繁に確認するなど、
視覚情報に頼って周囲の状況を把握することがより一層重要になります。
運転は私たちの生活において不可欠な移動手段であり、職域の拡大にも繋がる重要な要素です。
聴覚障害がある方も、適切な知識と対策をもって安全運転を心がけましょう。

まとめ
かつて運転が難しいとされていた聴覚障害のある方々も、
法改正により普通自動車や小型トラック、さらにはバスやタクシーの運転免許まで
取得できるようになり、 社会参加や職業選択の幅が大きく広がりました。
しかし、聴覚情報が制限される中での運転には、視覚による状況把握や周囲への配慮がより一層求められます。
ワイドミラーの使用や聴覚障害者マークの貼付といった工夫を通じて、安全運転を確保することが大切です。
運転は、生活の自由と社会参加を支える大きな手段です。
正しい知識と対策をもって、安全かつ自信をもってハンドルを握りましょう。