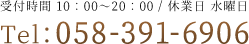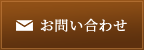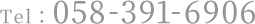こんにちは。
岐阜県羽島市の認定補聴器技能者の山村です。
「最近、聞こえづらい気がする」「家族の聞こえ方が心配」そんな不安を感じたことはありませんか?
難聴にはさまざまな種類があり、それぞれ原因や症状、対策が異なります。
この記事では、難聴の種類や特徴、原因、対策についてわかりやすく解説します。
1. 耳の構造による難聴の分類
難聴は、耳のどの部分に問題があるかによって、大きく3つに分類されます。
1-1. 伝音難聴
概要:外耳から中耳にかけての障害により、音が内耳に届きにくくなる状態。
主な原因:
-
中耳炎
-
鼓膜の損傷
-
耳垢の詰まり
-
先天性の耳の奇形
特徴:
-
小さな音が聞こえにくい。
-
大きな音でないと聞こえない。
-
医学的な治療(手術や薬物療法)で改善することが多い。
1-2. 感音難聴
概要:内耳や聴神経の障害により、音の信号が脳に正しく伝わらなくなる状態。
主な原因:
-
加齢(加齢性難聴)
-
長時間の騒音曝露
-
遺伝
-
ウイルス感染
特徴:
-
高音域から徐々に聞こえにくくなる。
-
言葉がぼやけて聞こえる。
-
医学的な治療が難しいが、補聴器の使用で改善が期待できる。
1-3. 混合性難聴
概要:伝音難聴と感音難聴の両方の特徴を持つ難聴。
特徴:
-
原因や症状に応じて、医学的治療や補聴器の使用を組み合わせて対処する。
2. 聞こえの程度による難聴の分類
日本聴覚医学会では、聴力の低下の程度により難聴を4つに分類しています。
2-1. 軽度難聴(25~40dB未満)
特徴:
-
小さな声や騒がしい場所での会話が聞き取りにくい。
-
会議や集団での会話で聞き返すことが増える。
2-2. 中等度難聴(40~70dB未満)
特徴:
-
普通の会話でも聞き取りにくくなる。
-
テレビの音量が大きくなる。
-
補聴器の使用が推奨される。
2-3. 高度難聴(70~90dB未満)
特徴:
-
大きな声でないと会話が難しい。
-
電話の着信音や呼びかけに気づかないことがある。
-
補聴器の使用が必要。
2-4. 重度難聴(90dB以上)
特徴:
-
補聴器でも聞き取りが難しい。
-
人工内耳の装用が検討される。
3. よく耳にする特定の難聴
3-1. 加齢性難聴(老人性難聴)
特徴:
-
年齢とともに聴力が低下する。
-
高音域から徐々に聞こえにくくなる。
-
左右の聴力が同じように低下する。
-
補聴器の使用で改善が期待できる。
3-2. 突発性難聴
特徴:
-
突然、片耳の聴力が低下する。
-
めまいや耳鳴りを伴うことがある。
-
早期の治療が重要。
3-3. 一側性難聴(SSD)
特徴:
-
片耳が著しく、または完全に聞こえなくなる。
-
音の方向がわかりにくくなる。
-
CROS補聴器の使用が有効。
3-4. 小児難聴
特徴:
-
生まれつきの難聴(先天性難聴)が多い。
-
言葉の発達に影響を与える可能性がある。
-
早期発見と適切な対応が重要。
4. 難聴を感じたら、まずは耳鼻科へ
聞こえに不安を感じたら、自己判断せずに耳鼻科を受診しましょう。
早期の診断と適切な対応が、聞こえの改善につながります。
5. 補聴器の活用
補聴器は、難聴の種類や程度に応じて、
聞こえをサポートする有効な手段です。
専門家と相談し、自分に合った補聴器を選びましょう。
まとめ
難聴にはさまざまな種類があり、それぞれ原因や症状、対策が異なります。
聞こえに不安を感じたら、早めに耳鼻科を受診し、適切な対応を行いましょう。
補聴器の活用も、聞こえの改善に役立ちます。